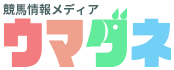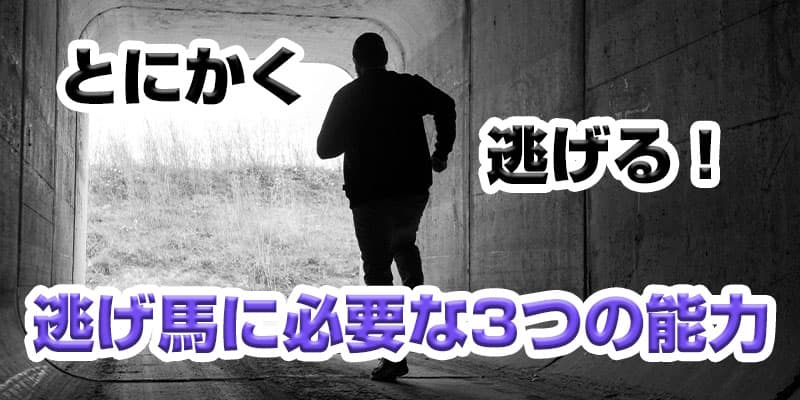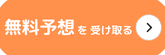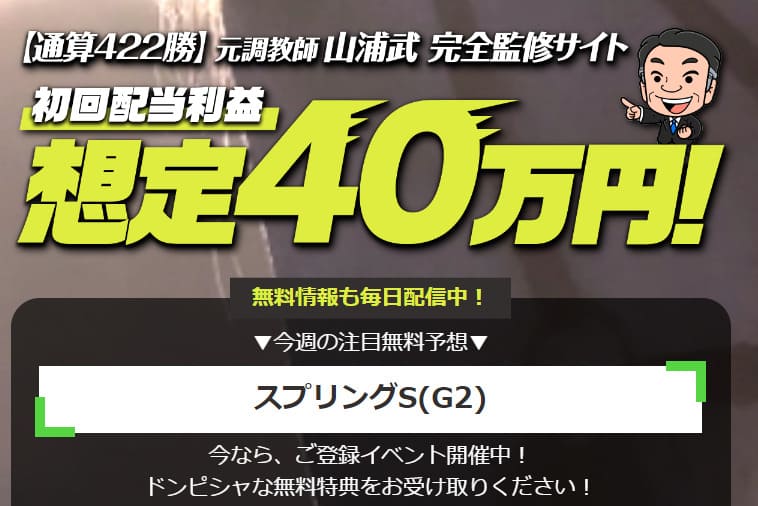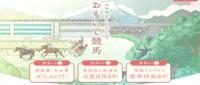当記事は、逃げ馬について競馬初心者でもわかるよう解説ていきます。
逃げ馬についての基本的な知識から、逃げ馬に求められる3つの能力、逃げ馬で勝負するべきレースなどについて解説していきます。
脚質について理解が深まればこれまで以上に多くの視点から競馬予想ができるようになるため、逃げ馬について詳しくなりたい方は是非当記事をご参考ください。
「とにかく的中を手にしたい!」「競馬で勝ちたい!!」
という人は、競馬予想会社の利用をおすすめします。
プロの馬券師による予想が手に入り、競馬初心者でも安定した3連単的中を実現可能。
また、基本的には『無料』の馬券予想プランも用意されているので、お試し感覚で登録することができます。
1:【疑問解決!】逃げ馬とは

はじめに、逃げ馬についての基本的な知識をまとめて解説します。
1-1:逃げ馬とはスタート直後から先頭に立ちレースを引っ張る馬
逃げ馬とは、スタート直後から先頭を目指し、レースを引っ張る走り方を得意とする馬のことです。
ちなみに、競馬用語で、単独で先頭に立って逃げることを「ハナ(端)を切る」といいますので、覚えておくとよいでしょう。
4つの脚質の中で最も単純な戦略に見えますが、レース全体のペースを決める役割を担うという見方もできます。
逃げ馬が速ければその後ろを走る先行馬も速いペースで走らなければならず、差し馬、追い込み馬のペースも必然的に上がります。
1-2:逃げが得意な名馬たち
天皇賞春 2017
キタサンブラック pic.twitter.com/QAuwu2abqA— Sleep (@horror_tripp) April 29, 2021
逃げが得意な名馬として挙げられるのは、まず第一にG1を7度制したキタサンブラックです。
逃げに限定せずとも名馬として名前が挙がる競走馬で、先行馬のイメージを持たれることもありますが、逃げも得意としていました。
実績はキタサンブラックと比べると劣りますが、逃げを得意とする名馬としてサイレンススズカ、ミホノブルボンといった名前が挙げられます。
こちらはいかにも逃げ馬といった走り方の割合が多く、逃げ馬といえばこちらを挙げる方も少なくないはずです。
1-3:逃げとは脚質の1つであり、脚質は全部で4種類または5種類
先述のとおり、逃げとはスタート直後から先頭を目指し、レースを引っ張る走り方を指します。
脚質は逃げ馬を含めて全部で4種類あり、それぞれ以下のような特徴を示します。
【逃げ馬】
スタートしてすぐに先頭に立ち、そのまま先頭をキープする
【先行馬】
逃げ馬を先に行かせ、逃げ馬のペースが落ちたら抜いて先頭に立つ
【差し馬】
前半は力を抑えて、最終コーナーから最後の直線で一気に抜き去る
【追い込み馬】
最後の直線まで最後方を保ち、最後に一気に抜き去る
この中でも逃げ馬は、2番以降を大きく引き離して逃げることを「大逃げ」と呼ぶこともあります。
逃げと大逃げは別の脚質として扱われることもあり、その場合は脚質は5種類になりますが、競馬新聞では一般的に先述の4種類が用いられます。
1-4:逃げ馬と先行馬の違いとは
レース序盤から先頭集団の中に入るという点では、逃げ馬と先行馬は共通しています。
主な違いとしては、先頭に立つかその後ろかという位置取りはもちろんですが、レース全体のペースを決める役割を担うかどうかが挙げられます。
逃げ馬は自分の走りがレース全体のペースを決める役割を担いますが、先行馬は逃げ馬に付いて行くような走りになるため、自分でペースを決めることはありません。
2:逃げ馬に求められる3つの能力

前章で紹介した逃げ馬の特徴を踏まえた上で、本章では逃げ馬に求められる3つの能力について解説します。
- 最初に一気に前に出る脚力
- 最後までペースを保つ持久力
- 終盤に後ろから迫られても最後まで粘る闘争心
それぞれを詳しく見ていきましょう。
能力①:最初に一気に前に出る脚力
逃げ馬に求められる能力その①は、スタート直後に一気に前に出る脚力です。
最初に先頭に立てないと自分のペースを作れないため、逃げ馬にとっては必須の能力となります。
脚力はもちろんですが、スタートダッシュの技術も重要です。
反対に、スタートが苦手な馬は逃げ馬として活躍するのは難しいといえます。
能力②:最後までペースを保つ持久力
逃げ馬に求められる能力その②は、終盤になってもペースを落とさず走る持久力です。
レース終盤では、差し馬や追い込み馬が追い上げてくるので、そこで疲れてペースが落ちてしまうと終盤に抜かれてしまいます。
最後まで逃げ切る持久力も重要な要素です。
能力③:終盤に後ろから迫られても最後まで粘る闘争心
逃げ馬に求められる能力その③は、終盤に後ろから迫られた時に最後まで気持ちの面で粘る闘争心です。
差し馬や追い込み馬は終盤まで力を温存して一気に勝負を仕掛けてくるため、ある程度距離が縮まるのは避けられないと考えた方がよいです。
逃げ馬は序盤から体力を消耗しやすいため、終盤に追い上げられた時、体力だけでなく、気持ちの面での粘りによる最後のもうひと伸びが勝敗を分けます。
気持ちの面での粘りや、粘りを生む闘争心も重要な要素です。
3:【必見】逃げ馬で勝負するべきレース

本章では、逃げ馬の特徴を踏まえた上で、逃げ馬で勝負するべきレースについて解説します。
逃げ馬は先頭に立ち、自分のペースで走ることが重要な脚質です。
そのため、他に逃げ馬がいると、逃げ馬同士で先頭の取り合いが起こり、自分のペースで走れなくなってしまいます。
このことから、逃げ馬で勝負する時は、他に逃げ馬がいない状況が望ましいといえます。
競馬新聞などを活用して全競走馬の脚質をチェックし、他に逃げ馬がいるかどうか確認することがポイントです。
また、競走馬だけでなく、競馬場も大きな影響を与えます。
一般的に、最後の直線が短いほど逃げ馬が有利になり、長いほど逃げ馬が不利になると言われています。
差し馬や追い込み馬は最後の直線で一気に勝負をかけてくるため、その距離が長いほど差し馬や追い込み馬にとってはチャンスが広がることになります。
差し馬や追い込み馬に追いつかれないために、最後の直線が短いかどうかのチェックも重要です。
4:やむを得ず逃げの戦略をとることもある
逃げを多用する競走馬は全て逃げが得意で選んでいるかというと、そうとも言い切れません。
逃げを選択する場合、消極的な理由の場合もあります。
それは、馬群の中に入るのが苦手な性格である場合や、自分のペースを乱されると途端にパフォーマンスが落ちてしまう性格である場合です。
逃げであれば馬群に入らずに自分のペースで走れるため、そのような性格でも影響を受けずに走ることができます。
見方を変えれば、馬群の中で走るのが苦手な性格の競走馬でも逃げなら勝負しやすいという点は、逃げのメリットであるといえるはずです。
まとめ
逃げ馬とは、スタート直後から先頭を目指し、レースを引っ張る走り方を得意とする馬のことです。
馬群に入らず、自分のペースで走れるというメリットを持つため、馬群の中で走ることが苦手な競走馬でも力を発揮しやすいというメリットを持ちます。
反面、序盤から先頭を目指すためスタミナの消耗が激しく、終盤に追い抜かれてしまうと逆転は難しいという点がデメリットだといえます。
このデメリットから、最後の直線が短い競馬場でのレースが逃げ馬にとって有利だと考えられます。
また、逃げ馬同士で序盤から先頭争いが生じると、自分のペースで走れるという逃げ馬のメリットがなくなってしまうため、他に逃げ馬がいない状況が望ましいです。
最後の直線が短い競馬場での、他に逃げ馬がいないレースがあれば、逃げ馬を軸にするチャンスだといえます。